
「教育資金を貯めるためには、学資保険に加入した方が良いのだろうか?」
「学資保険を選ぶ際には、どのような基準で判断すればいいの?」
お子様の未来のために、学資保険の加入を真剣に考えている方々が多いと思います。
学資保険はその特性上、一度加入すると見直しが難しいため、商品選びには慎重さが求められます。大切な資金を貯めるための保険ですから、失敗しない選択をしたいものです。
今回は、教育資金を学資保険で貯めることのメリットやデメリット、さらに学資保険を選ぶ際のポイントについて詳しく解説していきます。
学資保険は本当に必要か?

教育資金を貯める方法は、学資保険だけではなく、預貯金やつみたてNISAを活用するなどの選択肢も存在します。それでは、学資保険は本当に必要なのか考えてみましょう。
教育資金を学資保険で貯める際のメリットとデメリットを詳しく見ていきます。
学資保険のメリット
・貯蓄性がありリスクが低い
・契約者が万が一のことがあっても保障が続く
学資保険は、定期的に保険料を支払うことで強制的に貯蓄をしていく仕組みがあるため、貯蓄が得意ではない方でも安心して教育資金を確保できます。また、資産運用によるリスクもないため、安全に教育資金を形成したい方に非常に向いています。
さらに、契約者である親が保険期間中に不慮の死や高度障害状態になった場合、通常の保険料の支払いが免除されるため、保障も継続され、祝金や満期保険金も変わらず支払われます。
このように、契約者に何かあった際でも教育資金を確保できる点は、学資保険の大きな魅力の一つと言えます。
学資保険のデメリット
・自由にお金を引き出せない
・中途解約をすると元本割れの可能性がある
学資保険には、資産運用のような高いリターンは期待できません。つみたてNISAなどを利用して、多少のリスクを取ってでも効率的に教育資金を増やしたい方には向いていないと言えるでしょう。
また、学資金の受取時期は通常、子どもの進学時や満期に設定されているため、急にまとまったお金が必要になった場合でもすぐに引き出すことができません。
さらに、学資保険は満期まで契約を続けることが前提となっており、中途解約をすると元本割れを起こすリスクがあるため、加入前に保険料が家計に与える影響などを十分に検討する必要があります。
返戻率が低い学資保険は選ばないべき!

学資保険に加入することが決まったら、複数の保険会社を比較することが重要です。学資保険選びで特に重視すべきなのは返戻率です。貯蓄性を高めるためにも、保険の返戻率をしっかり確認することが大切です。
返戻率とは、支払った保険料に対して将来受け取れる保険金の割合を表しており、以下のように計算されます。
返戻率=受取総額÷払込保険料総額×100
返戻率が100%を超えると、支払った保険料よりも受け取る保険金が多いことを意味します。逆に、100%未満の場合は、支払った保険料よりも受け取る保険金が少ない元本割れの状態を示しています。
返戻率が高いほど貯蓄性が増しますので、同じ保障内容や保険金額であれば、返戻率の高い商品を選ぶ方が得策です。
保険会社が契約者から受け取った保険料を運用する期間が長くなるほど、返戻率は高くなります。したがって、払込期間を短縮したり、満期の時期を遅く設定することで、返戻率を向上させることも可能です。しかし、払込期間が短くなると保険料は高くなる傾向があるため、返戻率を上げることにこだわりすぎて家計に負担がかかっては意味がありません。無理のない保険料設定を心掛けましょう。
学資保険には、子どもが12歳まで加入できる商品や、祖父母でも契約可能な商品が存在しますが、状況によっては元本割れすることも考えられます。契約者や被保険者の年齢が高くなると、返戻率は下がる傾向にあります。そのため、返戻率を高めるためにも、学資保険にはできるだけお子様が小さいうちに加入しておくことが望ましいでしょう。出産予定日の140日前から契約できる商品も多いので、加入を考えている方は早めに行動することをお勧めします。
学資保険を選ぶ際のポイント

学資保険は返戻率以外にも、保険会社によって様々な特徴があります。選ぶ際には以下のポイントをしっかり押さえておきましょう。
貯蓄型か保障型かの選択
学資保険には貯蓄型と保障型の2つのタイプがあり、保障型には子ども向けの医療保障や育英年金などを特約として追加することが可能です。
貯蓄もできて保障も受けられる保障型は一見魅力的ですが、特約を追加すると返戻率が低下し、元本割れのリスクも高まります。
貯蓄性を重視するのであれば、シンプルな貯蓄型を選ぶことをお勧めします。
もちろん、子どもの将来を考え保障型を選ぶのも良いですし、貯蓄型を選択した上で別途医療保険に加入するという方法もあります。また、お住まいの地域で子ども医療費助成制度が充実している場合は、助成が終わった後に手頃な共済に加入することも選択肢に入れてみてください。
受取時期の重要性
学資保険に加入する際は、保険金の受取時期にも十分注意を払う必要があります。
お子様の誕生日や契約日によっては、18歳満期で設定すると大学入学前に保険金を受け取れない事態になることもあります。
学資保険の満期保険金は、満期日以降に支払われる仕組みですが、満期日とは満年齢になった後に初めて迎える契約応当日(契約日と同じ日)前日を指します。例えば、8月誕生日の子どもが学資保険に18歳満期で加入し、契約日が5月1日であった場合、大学1年生の4月30日が満期日となります。これでは入学後に受け取ることになり、入学金や受験費用を確保することが難しくなります。また、誕生日を迎えた後でないと保険金を受け取れないため、早生まれの子どもにとっては18歳満期だと入試前の受け取りが難しくなります。
このような事例を考慮し、17歳満期を設定している商品もあります。18歳満期で受け取りが遅れる場合は、17歳満期にして、高校3年生の時に確実に受け取れるようにする方が賢明です。満期の時期を十分に確認し、必要な時に学費を用意できるように設定することが重要です。
また、満期保険金の前に祝金を複数回受け取れる学資保険も存在しますので、祝金の受取時期は保険会社が決定したタイミングになります。そのため、この点についても担当者にしっかり確認しておくことが必要です。
まとめ
学資保険は大きな利益を生み出すことは期待できませんが、返戻率が100%を超える商品を選ぶことで、支払った保険料よりも多くの保険金を受け取ることが可能です。
支払い方法などを工夫することで、さらなる返戻率の向上も期待できます。無理のない範囲で設定を行いましょう。
保障内容をしっかり確認し、必要な時期に保険金を受け取ることができるようにしたいですね。
後で別のプランにすればよかったと後悔しないためにも、商品の特徴をしっかり把握し、最適な学資保険を選ぶことが重要です。

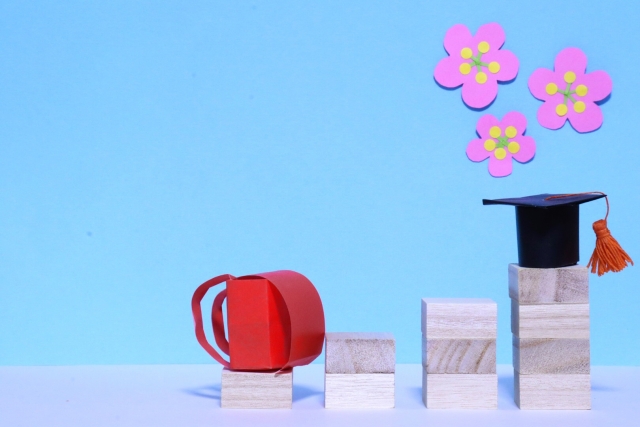


コメント