
最近、新しいライフスタイルとして注目されているものがあります。それは、移動が可能な家、すなわち『トレーラーハウス』です。
トレーラーハウスは、事務所や家の離れ、さらには子供部屋などとしても使える多様性を持っており、その特性上、アイデア次第で様々なシーンでの利用が可能です。
最近では「トレーラーハウスに住んでみたい」と希望する声も増加しており、伝統的な『一軒の家』ではなく、移動可能な『小さな家』というスタイルが広まりつつあるのです。
しかしながら、実際に購入する際には予期しない落とし穴が存在し、後悔することもあるかもしれません。
しっかりと下調べを行わずに購入することは絶対に避けてください!!
トレーラーハウスは、かなりの金額がかかる大きな買い物です。
この記事では、トレーラーハウスについて詳しくお話ししていきます。
そもそもトレーラーハウスってなに?
トレーラーハウスとは、『車輪がついていて、車で牽引可能な住まい』のことを指します。
タイヤを持つフレームの上に家の構造物が乗っているため、移動が可能なのです。
キャンピングカーを思い浮かべる方も多いかもしれませんが、実際には、移動するためには「建物を載せたフレームを車で牽引する」必要があります。これは、車の後部座席や荷台に設置された設備のあるキャンピングカーとは大きく異なる点です。
用途は多岐にわたり、カフェや店舗、オフィス、さらには別荘やセカンドハウスとしてトレーラーハウスを利用する人も多く、比較的長期間または恒久的に同じ場所に設置して使うことを想定しています。
お風呂やキッチン、トイレといった一般住宅と同じような設備が整っているため、トレーラーハウスだからといって特別な設備を準備する必要はありません。
言ってみれば、『タイヤのついたプレハブの家』といった印象ですね。通常の家と同じように生活するのに十分な機能を備えています。
土地さえあれば、日本全国を自由に移動し、定住することができるというのが大きな魅力です。
移動が可能であるため、グランピングやキャンプ場での宿泊施設としてもトレーラーハウスは非常に便利な『移動できる家』となっています。
トレーラーハウスのメリット
トレーラーハウスを利用することによって、どのようなメリットが得られるのでしょうか?
税制のメリット
トレーラーハウスは不動産とは見なされず、車両として扱われる可動産のため、固定資産税や不動産取得税の対象外です。
一般の住宅と同じように生活できる建物でありながら、車両として分類される理由は、建築基準法により、建物は地面に固定されている必要があるからです。
基礎や土台がないトレーラーハウスはこの条件を満たさないため、建物として認識されず、税金が課されることがありません。
固定資産税や不動産取得税を支払う必要がない生活なんて、まるで夢のようですね!
建物が建てられない土地でも大丈夫!
例えば、市街化調整区域など、建物の建設が禁止されている土地でも、トレーラーハウスは車両として扱われるため設置が可能です。建築確認や工事の手続きも不要で、さらに借地にも設置できるため、土地から土地への移動も自由自在です。
もちろん、定住する際にはライフラインも接続できるため、気に入った場所に長期的に住むことも可能になります!
住み心地は一般住宅と変わらない
トレーラーハウスは、一般住宅と比べるとサイズは小さいものの、外観は普通の住宅とほとんど変わらず、内装も『車』という印象はほとんどありません。キッチンやトイレ、お風呂、ベッドも完備されており、通常の生活を送るのに全く問題なく住むことができます。
間取りはトレーラーハウスの特性上、長方形になることが多いですが、間仕切りを工夫することで部屋数を増やせば、2人以上で暮らすこともできるのです。
自宅の庭に離れとして使ったり、子供部屋や趣味の部屋として活用することもでき、夢が広がりますね!
しかし、トレーラーハウスにはメリットだけではなく、もちろんデメリットも存在します。
魅力的なトレーラーハウスですが、一体どのようなデメリットがあるのでしょうか。
知らずに購入してはいけない事!注意点
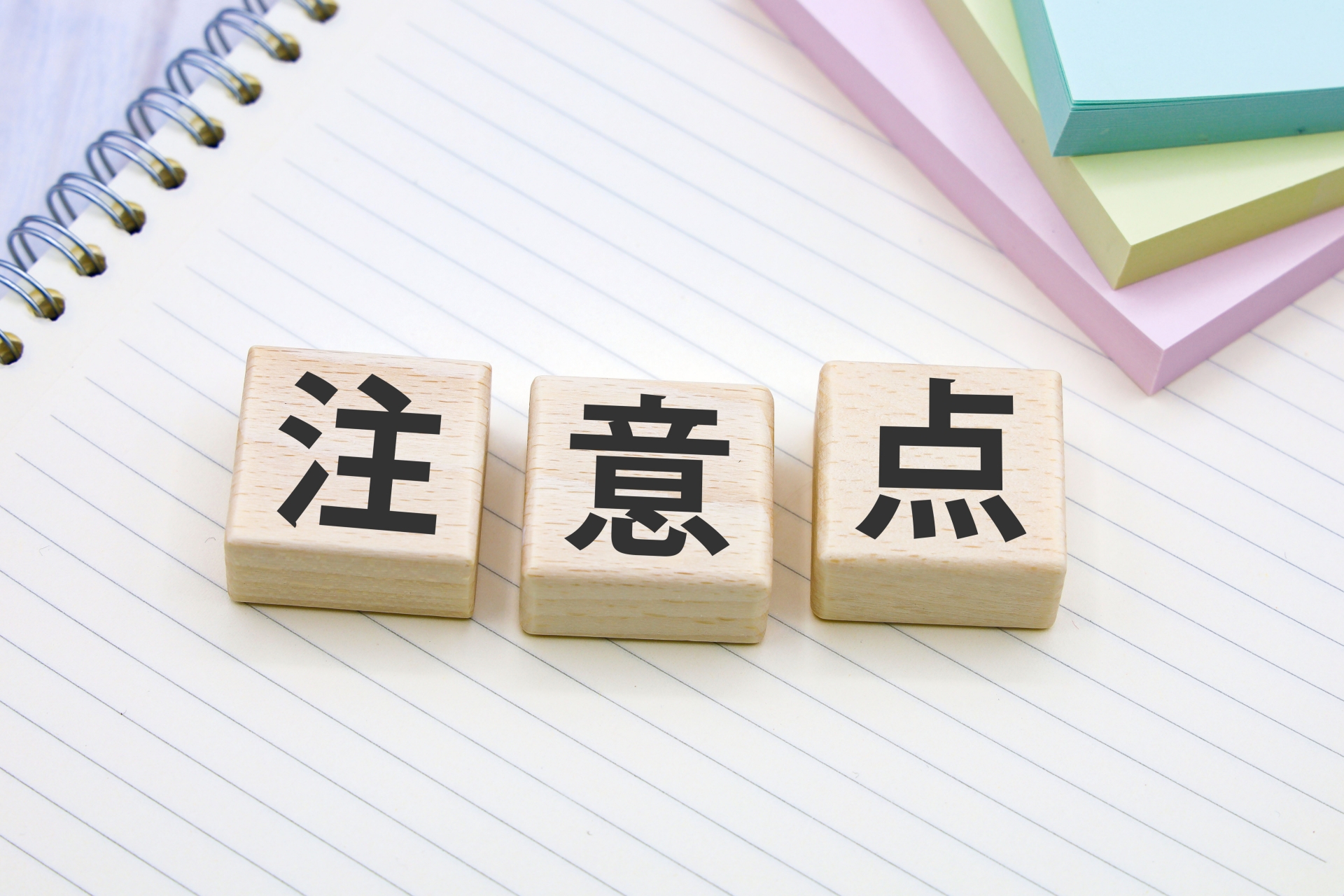
このように、夢のような生活が実現できるトレーラーハウスですが、しっかりと調査を行わずに購入すると、後悔することになります!
ここでは、注意すべきポイントをいくつかご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
間取りが不自由
トレーラーハウスは移動のために大きさに制限があります。公道を通る必要があるため、サイズには限界があるのです。
そのため、平屋程度の大きさに留まることが多く、二階建てや三階建て、あるいは横幅を広くすることは難しいでしょう。
このような理由から、大人数での生活には向かない間取りになってしまうのです。
トレーラーハウスには大きさに関する制限があるため、広々とした空間での生活を望む方には向いていないかもしれません。
車両扱いにするには条件がある!
トレーラーハウスを固定資産税のかからない『車両扱い』にするためには、いくつかの条件を満たす必要があります。
これは日本建築行政会議が定めた『車両を利用した工作物』に該当しない条件を意識することを意味します。
逆に言えば、これらの条件のいずれかを満たさなければ、建築物として扱われ、固定資産税が発生してしまうのです。
- 常に移動可能な状態で設置し、その状態を維持すること
- 水道・ガス・電気などのライフラインが、工具を使わずに接続・取り外しできること
- 適法に公道を移動できる車両であること
この3つの条件のうち、1つでも満たされない場合は車両として認定されず、建築確認を取得しなければ『違法建築物』となってしまいます。
タイヤがパンクしていたり取り外されている場合、またはポーチやベランダなど移動を妨げる設備がある場合、ライフラインが脱着式でない場合は認められないため、注意が必要です。
耐用年数が短く、定期的なメンテが必要になる
トレーラーハウスは、定期的なメンテナンスを行ったとしても、耐用年数はおおよそ20年程度に限られる可能性があります。
一般的な住宅とは異なり、基礎などの工事がしっかりしていないため、地盤が沈下してしまったり、支えているジャッキやタイヤの劣化が進むことがあるため、耐久性が低くなりがちです。
金属の土台に家が乗っている状態なので、雨風による錆の発生も懸念されます。そのため、長期間住むためには多くのメンテナンスが必要となり、その分の費用がかかることもあります。
トレーラーハウスをどれくらいの期間使用するつもりなのか、予算についてしっかり話し合う必要がありますので、どれだけの資金を準備できるのかを明確にしてから購入するのが良いでしょう。
設置や運搬費用が高額
トレーラーハウスの大きな魅力は自由に様々な場所へ移動できることですが、そのためには高額な費用がかかります。
運搬と設置には50万から80万円程度の費用がかかることが一般的です。さらに、設置する土地の状態によっては、コンクリートや砂利による『整地費用』も考慮する必要があります。
また、ライフラインを接続する際には、給水や排水、電気配線などの費用もかさむことが予想されます。
その他にも、牽引する車にかかる自動車税や自賠責保険、車検などの諸費用も発生します。
本体だけでも数百万円の費用が必要ですが、その他の費用もかかるため、『こんなはずではなかった!』と後悔しないためにも、予算は余裕を持って準備しておくことが無難です。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
トレーラーハウスは、車両としての条件を満たすことで、さまざまな場面で利用できる非常に魅力的な存在です。
住まいとしてだけでなく、オフィスや店舗として選ばれる理由の一つには、節税効果も大きく関わっています。
ただし、非常に便利な一方でデメリットも多く存在するため、計画的な購入が求められます。
『買わなければ良かった…』と後悔しないように、しっかりと下調べを行いましょう。
メリットとデメリットを踏まえた上で、自由で楽しい生活を手に入れてください。




コメント