長年勤めてきた会社を春になれば無事に退職し、新たなセカンドライフに思いを馳せてこの最後の秋を迎えている方も多いのではないでしょうか。しかし、退職後の資金面についてはどうでしょうか?
・老後2000万円問題
・少子高齢化による年金制度の揺らぎ
これらの日本が抱える構造的な問題に加え、今まで安定して得ていた収入が途絶えてしまうことに対して不安を抱く方も少なくないでしょう。このような不安に付け込んで金融商品を売り込むセールスマンがいることも事実です。
誰しも不安を感じると、冷静さを失い、思い切った決断を下してしまうことがあり得ます。大切な老後資金を守るためにも、銀行の営業員から推奨される商品についての知識をしっかりと身につけ、冷静に判断できるように心掛けましょう。
銀行マンの勧める好金利商品
リターンが高い商品には、必ず何らかのリスクが潜んでいるということを疑いの目で見ることが重要です。一般的に、金融の世界ではリスクとリターンは比例関係にあるため、高いリターンを追求する場合には、それに見合った高いリスクを取る必要があります。今回は、仕組み預金について詳しく解説していきます。
仕組み預金
仕組み預金の最大の魅力は、通常の定期預金の5倍から10倍程度の高金利で運用できることですが、それに伴うさまざまなリスクについても理解しておく必要があります。
銀行の営業担当者は、高金利を前面に押し出して営業を行ってくるため、その魅力的な部分だけを鵜呑みにして、退職金などの大切な資金を一気に運用してしまうと、取り返しのつかない事態になることもあるので、十分な注意が求められます。
一般的に、仕組み預金には以下のようなリスクが存在します。
①口座からの一定期間の引き出しを制約するタイプ
②元金割れの可能性を含むタイプ
この2つのタイプについて、具体的に詳しく見ていきましょう。
口座からの一定期間の引き出しを制約するタイプ
預金というものは通常、いつでも引き出せるものですが、このタイプの仕組み預金は、銀行側に満期の決定権があることが特徴です。
つまり、自分が引き出したいタイミングにお金を引き出せないということです。
通常の定期預金よりも金利は魅力的ですが、以下の点に注意が必要です。
①いつ引き出し可能になるか分からない
②運用面で不利な局面に陥る可能性がある
いつ引き出し可能になるか分からない
例えば、退職金1500万円を老後の資産形成のために仕組み預金で運用を開始したと仮定しましょう。満期は最短で1年から10年で、銀行側に決定権があるとします。
運用開始から2年が経過しました。しかし、銀行はすでに満期の延長を決定し、運用は3年目に突入しています。そんな時、息子から慌てた声で電話がかかってきました。どうやら交通事故を起こしてしまい、補償金を得るために700万円がどうしても必要とのことです。
この場合、緊急で引き出さなければならない事情が生じても、契約上、銀行から運用中のお金を引き出すことができません。仮に契約を破棄して元金を引き出すことが銀行と調整できたとしても、契約不履行の手数料が発生し、結果として元本割れを招くこともあるのです。
そのため、有事の際に必要な資金を考慮し、銀行側が提示する最長の運用期間でも余裕を持った資金配分を計算してから利用することが重要です。
運用面で不利な局面に陥る可能性がある
銀行側に満期日の決定権があるということは、契約時に定められた利率と将来の利率を比較し、銀行側が有利な選択をすることができるということを意味します。
例えば、契約当初に0.3%の固定利率で運用することが決定した場合、3年後に利率が0.5%に上昇したとしましょう。この場合、銀行側は当初の利率をそのまま据え置くことができるのです。その結果、仕組み預金を利用しないで運用していた場合に本来得られたであろう差額の利率0.5%-0.3%=0.2%の損失を被ることになります。
つまり、市場の金利状況に応じて有利な投資判断ができなくなってしまうため、その点を考慮して契約することが求められます。
元金割れの可能性を含むタイプ
預金は絶対に安全で、元本割れしないと誤解している人をよく見かけますが、本当に全ての預金が元本保証されているのでしょうか。
仕組み預金の中には、元本割れが起こりうる商品も存在します。これは、銀行が円で預かった資産を外貨で運用するもので、為替リスクを伴うため、高金利が適用されます。しかし、契約時に定められたレートと満期時のレートを比較した際、換金すると不利な通貨で銀行から元金が返却される可能性があるのです。
この点は少々複雑ですが、具体的に考えてみましょう。
例えば、契約時のレートが$1=150円、満期時のレートが$1=100円になった場合、ドルの価値が円に対して下がっています。この場合、満期時に元本として受け取れるのは、不利となる通貨であるドルです。
以下の点に注意が必要です。
①元本割れのリスク(外国通貨での元本受け取りの場合)
②為替差益を享受できないリスク(自国通貨での元本受け取りの場合)
外国通貨で元金が返却された場合
不利な通貨で返却される場合、外国通貨で返却された際に、自国の通貨にすぐ換金すると必ず為替差損が生じ、元本割れが発生します。
例えば、契約時のレートが$1=150円、満期時のレートが$1=100円の場合、契約時に150円を預けたとしましょう。この場合、満期時に返却されるのは1ドルです。
この1ドルを満期時にすぐに円に交換すると、100円になります。つまり、150円預けて100円を受け取る形となり、50円の損失が出てしまうのです。
自国通貨で元金が返却された場合
先ほどの例と同様の考え方で、別の例を見てみましょう。
例えば、契約時のレートが$1=150円、満期時のレートが$1=200円の場合、契約時に150円預けるとします。
この際、満期時に返却されるのは150円です。この場合、元本割れなしで好金利での運用が達成できた形になります。
しかし、ここで不思議なことに気づくかもしれません。ドルと円のレートが変化しているのに、受け取る元本の額は変わらないという点です。
実は、銀行側が利益を得る仕組みであることを示しています。銀行側は円とドルの交換による運用を行った際に、150円で1ドルを購入し、200円で1ドルを売ることで50円(運用益33%)の為替差益を得ているのです。
これは極端な例ですが、このような場合に自分で外貨の運用を行えば、仕組み預金の金利よりもはるかに高い運用益を得ることが可能だったのです。
仕組み預金の金利は、普通預金や定期預金と比較して高いものの、運用期間が短いことが多いため、実質的な運用益は数%程度となることが一般的です。例えば、仕組み預金金利が8%で1か月満期の場合、8%÷12か月=0.67%の運用益になります。
銀行側も収益を確保できるように計算を重ねて商品化しているため、この金利を支払ってでも為替の変動で利益を得ることができ、高金利に設定することが可能なのです。
まとめ(仕組み預金)

仕組み預金について、少しは理解が深まったでしょうか。以下にポイントをまとめましたので、本当に必要な時に購入するようにしましょう。
①仕組み預金には2つのタイプが存在する
(1)口座からの一定期間の引き出しを制約するタイプ
(2)元金割れの可能性を含むタイプ
②好金利であるが、それに見合ったリスクが存在する
◎自由に引き出せないリスク
◎元本割れのリスク
◎より有利な運用ができないリスク
最後までお読みいただき、ありがとうございました。

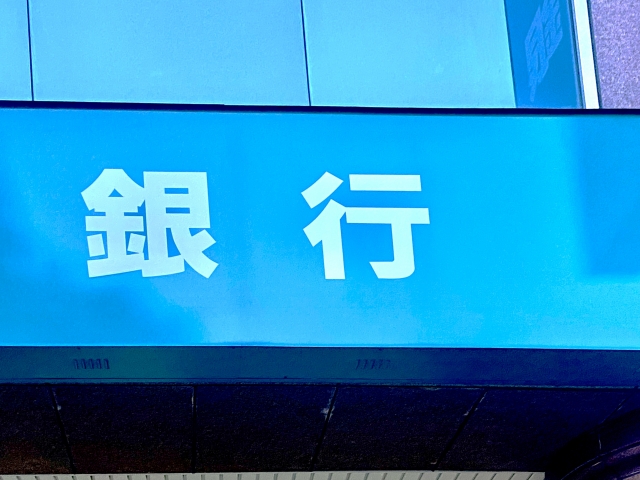



コメント