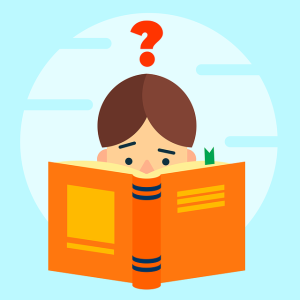
子どもが学習において行き詰まっているとき、あなたはどのように対処しますか?
学校での宿題だけで十分なのか、少し不安を感じることもあるでしょう。
市販のドリルは数多く販売されていますが、どれを選べば良いのか分からないという方も多いはずです。
ここでは、小学生のお子さんの学習を支援するために、市販のドリルを購入する際のポイントや注意点をまとめました。
子どもが勉強を嫌がらないように、適切に市販のドリルを活用する方法を見ていきましょう。
市販ドリルのメリット
種類が豊富
市販のドリルは、学年別や教科別に多くの種類があり、教科書の内容をわかりやすく解説したものが豊富に存在します。
また、問題をたくさん解きたいと考えているお子さん向けには、解説が少なめで練習問題が多く掲載されているドリルもあります。
基礎を固めるためのもの、応用問題や難問に挑戦するためのもの、学校のテスト対策用や受験対策用のものと、目的に応じて選択できるのが特徴です。
レベルも選べる
同じドリルでも、難易度はそれぞれ異なるため、選ぶ際には慎重に考える必要があります。
教科書の内容に基づいた基礎的なドリルは、学校の授業だけでは不安を感じる場合には特におすすめです。
イラストが豊富で詳細な解説がついているものをしっかり読み込むことで、授業で曖昧だった部分が明確になるでしょう。
学校の内容が理解でき、宿題もスムーズにこなせるお子さんや受験を考えている方は、応用問題が多く含まれる発展型のドリルを選ぶと良いでしょう。
教科書は一般的に中間的な学力に合わせて作られているため、難しい問題はあまり含まれていないのが実情です。
そのため、応用問題を正確に解ける能力が他の子どもたちとの差を生むことになります。
レベルアップを目指すお子さんや受験対策を考えている方にとっては、必須の選択肢となるでしょう。
お手頃な価格
書店で販売されている問題集は、一般的に1冊数百円から1,000円台と手頃な価格帯が多く、手に入れやすいのも嬉しいポイントです。
しかし、選んで購入しても、実際に使ってみたら子どもに合わなかったという経験も少なくありません。
まずは薄めのタイプのドリルに取り組んでみて、子どもがやりやすいと感じたら、同じシリーズの他の教科を追加で購入することで、無駄を減らすことができます。
市販ドリルのデメリット
市販のドリルを選ぶ際には、どのような点に注意すれば良いのでしょうか。
失敗したくない気持ちがある一方で、子どもが気に入ってくれるかどうか不安になることもあります。
ドリル選びで失敗を避けるためには、以下のポイントに気をつけて選ぶことが重要です。
子どもの学力のレベルに合ったものを選ぶのが難しい
購入時に中身を確認しても、果たして子どもの学力に合っているのかを判断するのは容易ではありません。
普段から子どもをよく観察し、どのような問題が苦手なのかを把握しておくことが大切です。
次々とドリルを買ってしまう
子どもは基本的に学校からドリルを宿題として出されることが多いですよね。
それだけでは不安を感じた親が市販のドリルを購入して取り組ませようとしても、なかなか最後までやり通すことができない場合が多いのではないでしょうか。
このタイプのドリルが合わなかったのか、または1冊では不十分なのかと次々に新しいドリルを与えてしまうと、子どもは中途半端に終わらせてしまったり、解説のニュアンスが微妙に異なったりして、余計に混乱を招くことがあります。
特にやりにくい場合でなければ、1冊のドリルをしっかりと最後まで終わらせることを心掛けましょう。
ご褒美型のドリルは内容が不足していることも
キャラクターが付いているものや、おまけの付録が多いドリルは、子どもの興味を引く一方で、学習内容がしっかりと習得できない場合があります。
勉強があまり好きではないお子さんにとっては、モチベーションを上げるためのきっかけにはなりますが、すべてが同じタイプではなく、問題数が多いものも併用することが望ましいでしょう。
選ぶときのポイントは

解説と問題数のバランスが良い
既に教科書で学んでいる内容に関しては、解説が細かすぎると逆に理解を妨げることがあります。
要点がしっかりと記載され、見やすいレイアウトになっていることが理想的です。
文字の大きさも、使用する子どもに適したサイズのものを選ぶことが重要です。
解説の後には必ず例題や練習問題があり、問題を解くことで理解度を確認できる形式のものがおすすめです。
色合いが派手すぎない
低学年向けのドリルの中には、非常にカラフルで絵本のようなものもあります。
目を引くデザインではありますが、子どもの集中力が色や絵に奪われてしまうため、あまり派手な色合いのものは避けるべきです。
1冊が厚すぎない
親としては、すべての内容が網羅されたものを購入したくなる気持ちも理解できます。
しかし、分厚いドリルは開きにくく、終わりが見えないため、途中で挫折してしまうことが多いのです。
算数のドリルなら、計算・図形・文章問題・単位換算・複合問題など、どの問題が苦手なのかをしっかり見極め、それに特化したドリルを選ぶことが大切です。
子どもに1冊をやりきったという達成感を与えることで、他の単元にも挑戦する意欲を引き出すことができるでしょう。
まとめ

市販のドリルを選ぶ際には、子どもの学力レベルに適したものを選ぶことが最も重要です。
苦手な単元に特化した薄めのドリルを1冊やりきることで、子どもに達成感を持たせることができます。
最初は親がそばで見守り、わからない部分を一緒に考えたり採点をしたりすることで、子どもは支えてもらっていると感じ、積極的に学習に取り組むようになるでしょう。
市販のドリルを効果的に活用し、子どもの学力向上に役立てていきましょう。

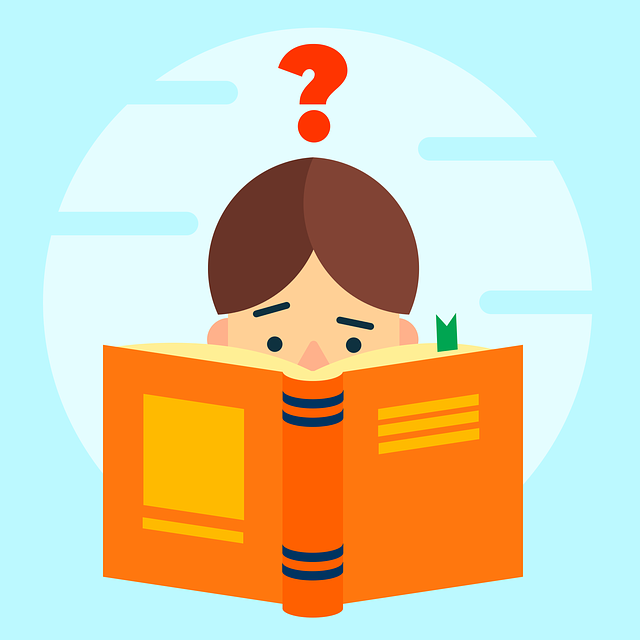


コメント